
提供価値の軸を変え、新たなニーズを開拓する。紙の器を美しく、使いやすい存在へと進化させた「WASARA」の軌跡
「紙皿」と言われると、どんなイメージを抱くでしょうか。ほとんどは、器の代用品、最低限の機能性が担保される使い捨てのモノという印象だと思います。
最近、紙皿という概念を超えたひときわ目を引く「紙の器」を創る企業が注目されています。その名も「WASARA」。ろくろを回して丁寧に作られた陶器を思わせる質感に、手にしっくりと馴染む滑らかなフォルム。従来の紙皿とは異なり、モノづくりへの真摯な姿勢が感じられます。
そんなWASARAを立ち上げた代表取締役の伊藤景一郎さんは、「前例のない挑戦なだけに何度も諦めかけた」と振り返ります。
どのように苦労を乗り越え、新たな価値を生み出したのか。THE BAKE MAGAZINEは、伊藤さんにお話を伺いました。

「チープで寂しい気持ちになる」。挑戦心に火を点けた一言
今日はよろしくお願いします!紙の器は「その場限りの使い捨て」というイメージが強かったため、細部にまで手が行き届いているWASARAを見たときは驚きました。
伊藤:ありがとうございます。私たちは「和の皿」をコンセプトに、陶芸技法の一つである手びねりで作られた陶器をイメージしながら製造にあたっています。現在は角皿や丸皿、ナイフやフォーク、コーヒーカップなど16種類を販売。
ご利用いただくのは立食でのパーティーシーンなどが多いので、お客様が持ったときにスマートに見えるデザインにしたり、ナイフやフォークに切れ目を入れてお皿と合わせて持ちやすいような形状にしたりと、工夫しています。

見た目の美しさのみならず、使いやすさにも配慮されているんですね。紙でここまでのこだわりを持って器を作るというのは、かなりの思い入れがないとできないことかと思います。なぜ伊藤さんは、WASARAを作ろうと思ったのでしょうか?
伊藤:私はWASARAを始める前から、伊藤景パック産業というお菓子のパッケージなどを開発する会社を経営しています。そのビジネスの中で、パッケージの価値に対して疑問を抱いていました。
お菓子メーカーは、販売価格を考慮すると製造コストの数%の金額しかパッケージにはかけられません。わずかなシェアをさらに多くのパッケージメーカーが奪い合い、価格競争になってしまう。
パッケージは本来もっと価値を発揮することができるポテンシャルがあるのに、価格で勝負せざるを得ない状況に課題を感じていました。
最初はお菓子のパッケージとしての可能性を模索されていたのですね。
伊藤:はい。葛藤を続けていたある日、尊敬する経営者の方に「実用的なものだけでなく、人に喜んでもらえるような商品を開発してみてはどうだろう」とアドバイスをいただいたのです。人に喜んでもらえたら、たしかに付加価値が生まれるかもしれないと考えました。とはいえ、明確なアイデアがあったわけではありません。ちょうどその頃、提供するパッケージの種類を広げてみようと、パーティーに使う紙皿や紙コップの仕入れや販売も始めるようになりました。そこでいただいたお客様の一言がヒントになったのです。
それは「貴社が仕入れた紙の器を使っているけれど、チープで寂しい気持ちになってしまう。せっかくならば、気持ちが明るくなるようなものを作ってみてくれませんか?」というご要望でした。安価なものでなく、食の場を彩るような気持ちが華やぐものを欲しているお客様もいらっしゃる。新たなニーズに気づいた瞬間でした。

紙の器に安さ以外の価値を求めるお客様がいると気づいたあとは、どうされたのでしょうか?
伊藤:私たちが価格競争をしている使い捨てのパッケージには、「安価で画一的」というイメージがつきまといます。しかし、視点を変えて「人に喜ばれる」「気持ちが明るくなる」ような商品を作ることができれば、価格競争から脱することができるのではと考えました。社内ベンチャーとしてWASARAを設立し、商品開発を始めたのです。
提供する価値を「安さ」という軸から、「喜び」などの別の軸へと変えていこうとされたのですね。商品開発はどのように進めていったのでしょうか?
伊藤:喜んでいただけるような器にするためには、美しいデザインと使い心地の良さが欠かせない。これを実現するためのコンセプトを考えるところから始めました。
想定していた商品の利用シーンは、パーティーやビュッフェなど。そこで大切なのは、持ちやすさです。日本では、お茶碗や湯飲みなど、手で包み込むように持つ食器がありますよね。こうした食器に対する日本らしさを、食器に反映させてみようと考えました。
そこで設定したコンセプトが「掌(たなごころ)」です。掌とは、手首から先の部位で、手を握ったときに内側になる面のことを指します。このコンセプトをもとに、持った時の触感や口触りなどが豊かになるように、日本人の価値観や美意識を込めようと商品開発を進めていきました。

実際にコンセプトを作り、形にしていく作業はかなり難しいものだと思います。どのように進めていったのでしょうか?
伊藤:WASARAの発案者であり、現在はプロデューサーの田辺三千代さんにデザイナーの緒方慎一郎さんを紹介してもらい、一緒に進めていきました。緒方さんは、デザイナーでありながら和菓子屋さんや和食店の経営もしていて、デザインワークとマネジメントの両方を実践している方です。デザインに関するコストをどう計算するかという悩ましい点においても理解のある方だったので、大変助かりました。
緒方さんからデザイン案を提案いただいて、イメージを形にするための方法を検討していきました。検討していった結果、採用したのが竹とバガスというサトウキビの搾りかすを使う方法でした。これらの材料は、環境に与える影響という観点からも理想に近かったのです。
どういった点が環境配慮につながったのでしょうか?
伊藤:竹は木に比べて成長が早いため、伐採が問題になる心配がありません。バガスは年間排出量が世界で1億トンとも言われていて、未利用のまま廃棄物として処分されることが多いのです。しかも、バガスの葉は広葉樹の繊維に似ていて、紙の原料としても十分に利用できます。
開発が始まった2005年は、温室効果ガス排出の削減を規定した京都議定書が発効されるなど、環境への配慮も叫ばれていました。今後、環境に配慮した素材での製造は欠かせない。その点からも、竹とバガスを使っての商品開発に挑戦しようと考えたのです。

理想とする商品を形にする上ではハードルもあったかと思います。どのように製造を行ったのでしょうか?
伊藤:パルプモールドという、和紙のようにパルプをすいて形をつくる製法で作っています。国内には食器用のパルプモールドの工場はなかったので、上海の工場で生産をしました。金網の内側に原料を溶かし込んだパルプを流し込み、乾燥する方法が一般的なのですが、どうしても表面に金網の跡がついてしまう。陶器のような手びねりの触感を再現するためには、従来の製法では不可能だったのです。
そこで、デザイナーと生産現場と一緒に検討を重ねました。パルプモールドで作るにはカーブが急すぎたり、不具合が発生して歩留まりが悪かったりと、製造の部分では大変苦労しました。関係者全員での試行錯誤の結果、網の外側にパルプを流し込み、内側から吸引する方式を発見。この方法であれば、金網の跡が表面につかないので、自由に模様を形作ることができます。
次に考えるべきは、表面のテクスチャーです。和紙や、手びねり、ろくろで作られた陶器のような3種類のテクスチャを用意しました。細かい凹凸ですが、これらをすべてCGでデザインし、日本で金型を起こしています。
工程に手間がかかっているので、通常の紙コップは1分間に250点できますが、WASARAは1点あたり90秒以上かかります。
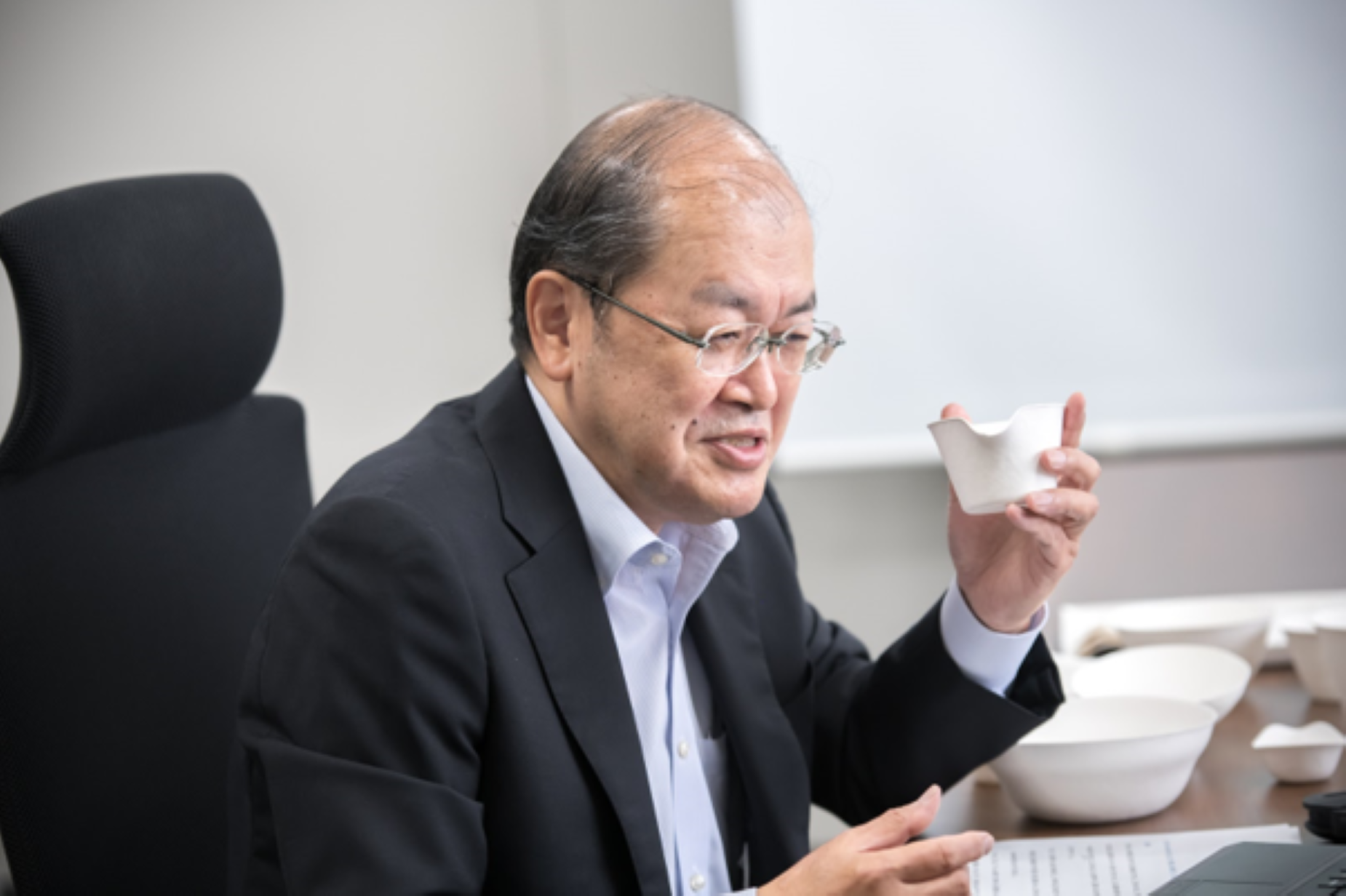
思い描いたモノを形にしようとすると、手間がかかるということでもあると思います。それだけの工数がかかってしまうと、コストもかなり高くなってしまうのではないでしょうか?
伊藤:そうですね。時には工場からの見積もりに対して、夜中まで交渉したこともありました。生産数が増えれば技術も習熟し安定していきますから、妥協はしませんでしたね。
コストだけでなく製法も考えぬき、技術指導を経て一定のクオリティで仕上げられるようになるまでに、1年半を費やしました。時には100点のうち85点が失敗してしまって、絶望の淵に立たされました。もう辞めてしまおうかなと(笑)。
それだけの苦労があっても、なぜ伊藤さんはあきらめなかったのですか?
伊藤:人が簡単に作れないものにこそ、高い価値がつくはずだと考えて踏ん張ってきましたね。もともと「高価でも人々に愛され、大切にされるものを作りたい」という思いは、幼い頃からあったのです。伊藤景パック産業は、私の祖父の代から続く会社。割り箸や経木など、1本あたり1〜2円のものを扱う中で育ってきたので、「いつか高価なものを作ってみたい」という憧れがありました。積み重ねた思いや憧れも、原動力だったのかもしれません。
こだわりを貫き、徹底的に商品を磨き続ける
ニーズの発見からコンセプトの設定、商品開発などの困難を乗り越え、商品を発表された後はいかがでした?
伊藤:商品のデザインと同様、緒方さんと各種クリエイティブやPR、販路など、議論して進めていきました。はじめから世界展開を見据えていたので、世界中の感度の高い人に広めて、話題喚起をしていきたいと考えていました。
狙い通り、海外での反応は非常によかったですね。2009年にはDesign For Asia Awardの大賞と金賞、2010年にはシカゴ建築デザイン博物館のグッドデザイン賞にも輝き、注目度はかなり高かったと思います。
注目は高まったものの、売上が伸びなかったんです。予想はしていましたが、案の定「高い」という声が後を絶ちませんでした。
それでも絶対に価格を下げたくはなかった。あせらず、地道にブランドイメージと商品を磨き続けていくことを選びました。

地道な改善はどのようなことを?
伊藤:例えば、使った時の満足感を磨きこもうと考えて、持ちやすさを意識したデザインの商品を開発しました。元々はまっさらなお皿だったものに、醤油やソースを入れるための窪みを作りました。
商品の大事な点である使いやすさへの工夫をこらしていったのですね。価値をあげていくために、その他に取り組まれたことはありますか?
伊藤:まず、使ってもらって手触りや口当たりを体験してもらわなくては、WASARAの価値は伝わりません。そのため、パーティで無償で振る舞い、営業につなげるなど地道な活動を続けていきました。フランス大使館や羽田空港のラウンジなど、利用してくださる取引先も増え、少しずつ売上が上がっていきました。テレビなどのメディアに取り上げられて認知がさらに広がっていったこともあり、19年にはようやく黒字に転じました。
2008年のリリースから10年以上かかりましたが、資金が持つ限りは続けようと本業のパッケージとの兼ね合いを見ながら調整を続け、諦めなかった甲斐がありました。

「WASARA」という新たな器のジャンルを確立させる
最近では、なにか変化はありますか?
伊藤:従来どおりのケータリングでの利用はもちろんですが、レストランなどでの定常的な導入が増えています。ニューヨークのブルックリンにある「750 MYRTLE DINER」というレストランでは、オープン当初から全ての食器にWASARAが使われていますし、新橋にあるダイニングレストランの「旬八キッチン&テーブル」でも、全ての皿がWASARAになっています。

レストランでの導入が増えているのはなぜなのでしょう?
伊藤:一つは、人件費や水道代といったコストの削減ですね。例えばWASARAを導入いただいている「旬八キッチン&テーブル」では、通常の食器を使っていると、配膳を担当するスタッフの他に食器を洗うスタッフを1人〜2人ほど配置する必要がありました。営業終了後に食器を洗ったり置き場に戻したりすると、片付けに1時間ほどかかってしまう。WASARAを使えば、だいたい10分ほどで片付けが終了します。収納スペースの確保や水道代の節約にもつながっているという声もあります。
もう一つが環境への配慮です。こうした紙の皿の使い捨ては従来の紙の皿であれば罪悪感や環境への影響が問題視されます。しかし、WASARAは製造過程での環境負荷も抑えていますし、埋めれば90日で分解されて土に還ります。WASARAが分解されて作られた肥料も売られているのです。WASARAを使うことで、環境にも配慮しているという姿勢を示す目的で使うレストランもあります。

コスト面での利点に加えて、WASARAが掲げている価値観に共感するレストランが増えているのですね。
伊藤:はい。食器をWASARAに置き換えるという流れが生まれつつあった中で、新型コロナウイルスが流行。営業時間を短縮したり、受け入れるお客様の数を減らしたり、働くスタッフも密にならない配慮をする必要があるため、人件費の削減が急務です。そこでWASARAの注目度が上がったのか、ラグジュアリーホテルやレストランからの問い合わせがさらに増えました。

今回の導入をきっかけに紙の器の良さが伝われば、「WASARA」という一つの食器のジャンルが生まれるのかもしれないと考えるようになりました。配膳や洗う手間など、既存の食器が持つ課題は大きい。WASARAを使うことでそういった手間が解消されて、浮いた分のコストを食そのものに還元できる可能性もありますよね。
食器の役割や食器に対する認識の仕方が変わりそうですね。
伊藤:料理を提供された側も、WASARAの存在で紙の器に対する固定観念が崩されるかもしれません。実際に見て手で触ってみた時に、「これが紙でできているのか」という驚きにつながれば、食の体験がとても面白くなるはずです。WASARAという新たな食器のジャンルを確立させて、紙の器の意味を問い直していきたい。これが、私の密かな野望です。

今回お話しをお伺いする中で、確かなコンセプトと実直にモノ作りに向き合う姿勢こそが、イノベーションを起こす上で欠かせないと感じました。紙の器が既存の食器の代用品ではなく、一つのジャンルとして確立される未来がすぐ近くに来ているのかもしれません。伊藤さん、ありがとうございました!
| ★ WASARAさんへのお問い合わせ・ご注文はこちら |
